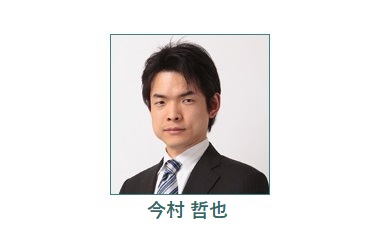━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン No.425 2025/7/3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】今村先生のイギリス著作権法の特徴を捉える(初級編)
【2】【7/31・8/20 開催】全国オンライン著作権セミナー開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
本日7月3日は「通天閣の日」
1912年のこの日、大阪市浪速区に通天閣が完成し、1903年の第5回内国勧業博覧会会場跡地の西半に娯楽地「新世界」を開発した際、その中心にパリのエッフェル塔を模して作られたそうです。
さて、今回は今村哲也先生のイギリスの著作権制度についてです。
今村先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/imamura/
◆◇◆イギリス著作権法の特徴を捉える(初級編)━━━
Chapter 36. イギリスのサイトブロッキング制度
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
明治大学 情報コミュニケーション学部 教授 今村哲也
1. はじめに
インターネット上の特定サイトへのアクセスを遮断する「サイトブロッキング」は、インターネット上に流出した児童ポルノコンテンツが掲載されたサイトや著作権侵害サイトへの遮断といった海賊版対策を目的に各国で導入されている措置です。イギリスでは、著作権侵害について、法制度に基づくサイトブロッキングが早くから運用されており、表現の自由との調和やコスト負担の問題も含め、多くの議論を経て制度が確立しています。
一方、日本では、児童ポルノ流出防止対策のためのサイトブロッキングは、ISP事業者の自主的な取り組みとして長らく実施されています。しかし、海賊版サイトについては基本的に実施されていません。
2018年の「漫画村」事件を契機に著作権侵害に対するサイトブロッキングの導入について議論されましたが、法的なハードルが高く導入には至りませんでした。
他方で、最近になって、オンラインカジノサイトへのブロッキングについて総務省を中心に議論されているところです。
今回は、裁判所の関与、 実施主体、 表現の自由、 コスト負担の観点から、著作権に関するイギリスのサイトブロッキング制度について説明したいと思います。
2. 裁判所の関与:サイトブロッキング命令の取得プロセス
イギリスでは著作権法(CDPA1988)第97A条や第191JA条に基づき、権利者(著作権者や商標権者など)が裁判所に対しサイトブロッキングの差止命令(injunction)を求めることが可能です。
これらの規定の目的は、インターネット上の権利侵害行為を最も止めやすい立場にあるサービス提供者(通信事業者)に対し、裁判所が差止命令を出せるようにすることにあります。
したがって、サイトブロッキングを実施するには必ず司法の関与(裁判所での手続)が必要であり、裁判所が命令発出の是非を判断します。
裁判所は命令を出すにあたり、対象サイトが大規模かつ明白に違法なコンテンツを提供していることなどを慎重に審査します。その上で高等法院(High Court)が差止命令を認めれば、命令が主要ISP(ブリティッシュ・テレコムBTやスカイなど国内大手プロバイダ)に送達され、各ISPは自社のネットワーク上で指定サイトへのアクセス遮断を実行します。
例えば、2013年のParamount Home Entertainment International Ltd v British Sky Broadcasting Ltd [2013] EWHC 3479 (Ch)では、高等法院が主要6社のISPに対し映画やテレビ番組のストリーミングへのアクセス提供についてアクセス遮断を命じました。
3. 実施主体:誰がブロッキングを行うのか
イギリスではサイトブロッキングの実務的な担い手はインターネット接続事業者(ISP)です。裁判所の命令は特定サイトへのトラフィックを遮断する措置をISPに取らせるものであり、実際のブロック(アクセス遮断)の技術的実装は各ISPが行います。
対象となるサイトは多くの場合、海外にサーバを置く海賊版サイトや違法コンテンツ配信サイトであり、国内法の執行が及びにくいものです。ISP各社は命令に従い、DNSブロッキング・IPアドレスブロッキング・URLフィルタリング等の技術を駆使して、ユーザーから該当サイトへの通信を遮断します。
ブロッキングの方法は事案によって裁判所が指定することもあります。たとえばNewzbin2事件では、対象サイトのIPアドレスが他の合法サイトと共有されていたため、過剰ブロッキング(over-blocking)を避ける目的でIPアドレスの経路変更(リルーティング)と深層パケット検査(DPI)によるURLブロックを組み合わせる手法が命じられました(Twentieth Century Fox Film Corp. v. British Telecommunications plc (No. 2) [2011] EWHC 2714 (Ch) (‘Newzbin2 [No2]’)。)
一方、Pirate Bay事件では対象IPが他サイトと共有されていなかったため、単純なIPブロッキングが命令されています(Dramatico Entertainment Ltd v British Sky Broadcasting Ltd [2012] EWHC 1152 (Ch) (‘Dramatico [No 2]’))。
このように裁判所の判断に基づき技術手段が選択され、ISPは自社の設備でブロックを実施します。
なお、イギリスのISPは児童ポルノ対策としてInternet Watch Foundation (IWF)のリストに基づくURLブロッキングシステムを以前から自主導入しており、その延長で著作権侵害サイトの遮断にも対応してきた経緯があります。結果として、実施主体は民間のISPですが、その行為は個々の裁判所命令により法的に裏付けられています。
4. 表現の自由への配慮:過剰ブロックと検閲の懸念
イギリスには成文憲法はありませんが、欧州人権条約(ECHR:European Convention on Human Rights)第10条を国内法化した人権法により「表現の自由」が保障されており、サイトブロッキングに際してもこれを侵害しないよう配慮がなされています。
裁判所はブロッキング命令を出す際、比例原則(proportionality)の審査を行い、措置が必要かつ適切であるかを検討します。
具体的には、ブロック対象サイトに合法コンテンツが含まれる割合や、正当な情報流通への影響を評価し、過度に広範な遮断とならないよう注意します。
命令の内容も必要最小限に限定され、例えば特定ドメイン名や特定URLへのアクセスのみを遮断し、それ以外の無関係な通信への影響が出ないよう技術的手段が選択されます。
裁判例でも、非侵害コンテンツへのアクセスが不当に妨げられてはならない、との考慮が示されており、過剰ブロッキング(over-blocking)の回避が重視されています。
5. コスト負担:ブロッキング実施にかかる費用の扱い
サイトブロッキングの実施には技術的なコストが発生します。たとえば、ブロッキング用フィルタリングシステムの導入・維持費、ネットワーク設備の設定変更にかかる人件費、管理コストなどです。
当初、イギリスではこれら実施コストを誰が負担すべきか明確ではありませんでした。2014年のカルティエ事件一審・二審(商標権侵害の模倣品販売サイトへのブロッキングに関する事案)では、裁判所は、ブロッキングの実施に関する実施費用はISPが負担すべきとの判断を示しました。
しかしISP側はこれを不服として上告し、2018年に連合王国最高裁判所(Supreme Court)は画期的な判断を下しました。最高裁は、サイトブロッキング命令の実施費用は、本来侵害者(サイト運営者)が負うべきものであり、侵害に無関与のISPに負わせるのは公平でない、とし、権利者がISPに対し合理的な範囲でコストを補償すべきと結論付けたのです(Cartier International AG and others v British Telecommunications Plc and another [2018] UKSC 28)。
つまり、ブロッキング命令を求めた権利者側が費用を負担する原則が確立されました。この判断の背景には、英国法上の一般原則として、無関係の第三者に負担を強いる場合は、勝訴当事者が費用を補填する、という考え方があります(ノーウィッチ・ファーマカル命令などで確立された法理)。
最高裁はISPを「単なる通信のパイプ役(mere conduit)」と位置付け、違法行為に直接関与しない者に自費で対策を講じさせるのは不当と断じました。
この結果、以後イギリスではブロッキング命令に伴うISPの実費(フィルタリング装置の費用等)は基本的に申立てを行った権利者(映画会社やレコード会社など)が負担することになりました。
ただし補償すべき費用は「合理的な範囲内のコスト」に限られます。これは、過度に高額なシステム導入費などまで全額請求できるわけではなく、ケースごとに裁判所が妥当な範囲を判断するという意味です。
総じてイギリスでは、サイトブロッキングは権利者自らの負担で行う私的救済の一種という位置付けになっていると言えます。
6. おわりに
以上のように、イギリスはサイトブロッキング制度を司法の統制下で安定的に運用しており、表現の自由への配慮や費用負担のルールも整っています。
日本は法制度の空白があり、通信の秘密という高いハードルもあって慎重姿勢が続いています。サイトブロッキングの導入については慎重な判断が求められるところですが、漫画作品などの海賊版による被害が深刻化する中で、総合的対策の必要性は認識されています。
ところで、2025年1月になり、米国下院でも、「外国デジタル海賊行為防止法案(Foreign Anti-Digital Piracy Act, FADPA)」が提出されました。この法案は、イギリスなど各国の制度にならって、米国内の著作権者が米連邦地方裁判所に申し立てを行い、海外に拠点を置く海賊版サイトへのアクセス遮断命令(ブロッキング・オーダー)を取得できるようにするものです。
我が国でも、国内のエンターテイメント市場を守るために、今後の立法政策の論点の一つとして、国内の消費者が適法なサイトからコンテンツを消費するという意味で効果的な海賊版対策のあり方について、さらなる議論がなされるべきなのではないかと思われます。
参考文献:
今村哲也「イギリスにおけるサイトブロッキング」知財学会誌16巻3号(2020年)
今村哲也「Cartier International AG and others v British Telecommunications Plc and another [2018] UKSC 28」SOFTIC Law News No.161(2018年)
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【7/31・8/20 開催】全国オンライン著作権セミナー開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
このたび、全国の官公庁・民間企業の皆様を対象に、著作権に関する実務セミナーを開催いたします。
情報発信の多様化やデジタル化が進む現代において、著作権の適切な理解と対応は、業務運営上ますます重要性を増しています。
今回は、著作権のより一層の保護を図るために、著作権の基礎知識の普及と複製を行う際に必要となる契約についてご案内させていただきます。
また、一般的な著作権(初級レベル)についての解説や著作物の正しい利用方法についてより詳しくご説明いたします。
〇開催要項
日 時 :【第1回】7月31日(木) 14:00~15:30
【第2回】8月20日(水) 14:00~15:30
会 場 :オンライン (Zoom/YouTube)
参加費 :無料
主 催 :公益社団法人日本複製権センター
参加協力:新聞著作権協議会(加盟68社)および日本経済新聞社、奈良新聞社
〇プログラム(予定)
【第1回】
トピックス1 著作権の集中管理と適正利用について
トピックス2 新聞の紙面ができるまで
トピックス3 新聞記事を巡る著作権侵害の事例 ~リスクを避けてクリッピング活用を~
トピックス4 著作物の複製等に関する利用許諾の取得について
【第2回】
トピックス1 著作権の集中管理と適正利用について
トピックス2 新聞の紙面ができるまで
トピックス3 新聞記事を巡る著作権侵害の事例
トピックス4 著作物の複製等に関する利用許諾の取得について
参加お申込みページ:https://jrrc.or.jp/event/250703-2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。
□読者登録、配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、HPよりお申込みください。
(見積書の作成も可能です)
⇒https://jrrc.or.jp/
ご契約窓口担当者の変更
⇒https://duck.jrrc.or.jp/
バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
お問い合わせ窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/