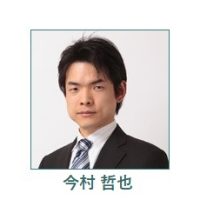━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン No.426 2025/7/10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、 関係者の方にお送りしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】井奈波先生の 欧州AI規則の解説
【2】【8/6開催】 JRRC 著作権講座初級オンライン開催について
【3】【7/31・8/20 開催】全国オンライン著作権セミナー開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
本日7月10日は「四万六千日」
浅草・浅草寺の縁日で、この日に参詣した者には4万6千日参詣したのと同じご利益や功徳があるとされています。
本来は7月10日だけであるが、9日から行われる「ほおずき市」に合わせて9日にも法要が行われているそうです。
さて、今回は井奈波先生の「 欧州AI規則の解説」 です。
井奈波先生の前回の連載は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/inaba/
━━ ◆◇◆【1】井奈波先生の 欧州AI規則の解説━━━
第3回 AIシステムとは
━━━━━━━━━ ━━━━━━━ ━━━━━━━━ ◆◇◆
今回は、どのようなAIシステムが、AI 規則で規制の対象となる「AI システム」の定義(AI規則3条(1))に該当するのかについてみていきます。この定義については、 AI規則前文12項に説明があり、さらに、定義の解釈についてガイドラインが公表されています(以下、単に「ガイドライン」といいます)。
ガイドライン:https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-ai-system-definition-facilitate-first-ai-acts-rules-application
AI規則はあらゆるAIシステムを適用対象とするのではなく、AIシステムの定義に該当するものだけを対象としますので(ガイドライン2項)、定義の解釈が重要となります。しかし、このガイドライン自体が、AIシステム該当性の自動的な判断や限定列挙は不可能としており(ガイドライン 6項、62項)、ガイドラインを参照に自分で判断するように、というスタンスといえます。
1 AIシステムの定義
そもそもAIは、学者によって定義が異なる状況です(総務省情報通信白書)。しかし、法律にする場合、一定の定義が必要になります。AI規則におけるAIシステムの定義は、OECDの定義(2019年)を参照にしたものですが、OECDの最新の定義( 2024年)は、逆にAI規則の影響がみられます。
表3-1 法律におけるAIシステムの定義(下線筆者)
| AI規則の定義 | 「さまざまなレベルの自律性で動作するように設計され、その導入後に適応性を示し得るものであり、かつ明示または黙示の目的のため、受け取った入力から、現実のまたは仮想の環境に影響を与えうる予測、コンテンツ、提言または判断などの出力を生成する方法を推論するものである、マシンベースのシステム」(3条(1))。 |
| 【参考】 OECDの定義 |
「AIシステムとは、明示または黙示の目的のために、受け取った入力から、予測、コンテンツ、提言または判断のような、現実のまたは仮想の環境に影響を与え得る出力を生成する方法を推論するマシンベースのシステムである。各種のAI システムにより、導入後の自律性および適応性のレベルは異なる。」(2024年3月5日付公表) 2019年の定義:「AIシステムとは、人間が定義した一定の目的のために、現実または仮想の環境に影響を及ぼす予測、提言または判断を行うことができるマシンベースのシステムをいう。AIシステムは、マシンおよび/または人間による入力を用い、現実のおよび/または仮想の環境を認識し、それらの認識をモデルに抽象化し(たとえば機械学習などによる自動的な方法または手動で)、モデル推論を用い、情報または行動の選択肢を公式化する。AIシステムは、さまざまなレベルの自律性で動作するように設計される」 |
| 【参考】 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(日本)の定義 |
この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。 |
(引用元)OECD 「EXPLANATORY MEMORANDUM ON THE UPDATED OECD DEFINITION OF AN AI SYSTEM」
https://www.oecd.org/en/publications/explanatory-memorandum-on-the-updated-oecd-definition-of-an-ai-system_623da898-en.html
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/06/artificial-intelligence-in-society_c0054fa1/eedfee77-en.pdf
以上のとおり、OECDの定義とAI規則はAIシステムについて、同じ考えを採用しているといえます。AI規則は、マーケットベースアプローチを採用し、取引の対象となるAIシステムを規制するのに対し、我が国の上記法案の場合、技術開発・活用推進を目的とするので技術に着目した定義がされている点が大きな違いといえます。
2 定義の7要素
AI規則におけるAIシステムの定義は、次の7要素に分解されます(ガイドライン9項)。ただし、これらの7要素は、AIシステムの構築段階および使用段階を通じて、常に存在する必要はないとされます(ガイドライン 10項)。
表3-2 定義の7要素
| ① マシンベースのシステムであること ② さまざまな自律性で動作するよう設計されていること ③ 導入後に適応性を示し得るものであること ④ 明示または黙示の目的のためであること ⑤ 受け取った入力から出力を生成する方法を推論するものであること ⑥ 予測、コンテンツ、提言または判断などの出力を生成するものであること ⑦ それが現実のまたは仮想の環境に影響するものであること |
(1) マシンベースのシステム
マシンベースのシステムとは、AIシステムがマシン上で動作することを意味します(前文12項)。マシン、といってもハードウェア・コンポーネント(コンピュータ計算のためのインフラ)だけでなく、ソフトウェア・コンポーネントを含みます。(ガイドライン11項)。
(2) 自律性
自律性は、AIシステムが人間の干渉からある程度の独立性を有し、人間の介入なく動作する能力を有することを意味します(前文12項)。AIシステムは人間と機械との協働を前提とし、協働には様々な程度があるのですが、この要件により、すべてのタスクを手動により操作するシステムは除外されます。
(3) 適応性
適応性は、AIシステムの使用中にシステムの変更を可能とする自己学習能力を意味します(前文12項)。システムに同じ入力をした場合でも、自己学習能力により、異なる結果を生成する可能性があることです。ただし、これは必須の要件ではないとされます(ガイドライン23項)。
(4) 目的
AIシステムは、明示または黙示の目的(objectives)に従って動作するものであることが求められます(前文12項)。AIシステムの目的(objectives)は、AIシステムの意図目的(intended purpose)とは異なる概念で、両者は異なる場合があるとされます(前文12項、ガイドライン25項)。意図目的は、「提供者がAIシステムの目的とする使用」と定義され( AI規則3条(12))、システム設計の目的(たとえば特定の業務支援)など、システムの外部において設定される目的を意味します。これに対し、AIシステムの目的(objectives)は、システム内部の問題であり、明示的に設定される目的の例として、累積報酬(強化学習において得られる報酬の合計値)の最適化などが挙げられています(ガイドライン24項)。
(5) 出力を生成する方法を推論できること
推論能力は、AIシステムの本質的な特徴とされます。推論能力とは、「現実の環境や仮想の環境に影響を与え得る予測、コンテンツ、提言または判断などの出力を生成するプロセスと入力やデータから、モデルやアルゴリズム、またはその双方を推論するAI システムの能力」をいいます(前文12項)。AIの使用段階における出力を生成し結果を推論する能力だけでなく、 AIの構築段階も含む概念とされ(ガイドライン27項~29項)、構築段階における推論を可能とする技術として、機械学習と知識ベースまたは論理ベースのアプローチが挙げられています(前文 12項)。
(6) 予測、コンテンツ、提言または判断などの出力を生成するものであること
予測、コンテンツ、提言または判断などの出力を生成する能力は、AIシステムの基本となります。コンテンツは2019年のOECDの定義に入っていませんが、見直し後の定義とAI規則の定義ではコンテンツの生成も挙げられています。これは、2019年以降における ChatGPTなどコンテンツ生成AIの普及を受けたものです。
(7) 現実のまたは仮想の環境に影響
AIシステムが、物理的環境や仮想環境に能動的に影響を及ぼすことを示すものです。リスクベースアプローチに由来すると考えられます。
3 AIシステムに該当するもの・該当しないもの
最後に、何がAIシステムに該当し、何が該当しないのかについて、ガイドラインに示されている例を挙げます。ざっくりまとめると、ポイントは推論の有無で、計算結果に基づく出力を行うに過ぎないシステムは、AIシステムの定義から外れるといえそうです。
(1) AIシステムに該当するものの例
① エキスパートシステム:人の手でルールや知識を入力し、それをもとに推論エンジンが推論し、結論を導き出すことができるシステムで、専門家のように推論したり判断したりできることから、エキスパートシステムといわれます。人間による知識やルールの入力(知識ベース・ルールベース)が必要ですが、自動的に推論や判断ができるので、自律性が認められます。これは、1980年代の第二次人工知能ブームの際に注目されたシステムです。
② 機械学習:2000年代から現在まで続く第三次人工知能ブームの火付け役となった技術で、ある目的を達成する方法をデータから学習するものです。機械学習には、教師あり学習、教師なし学習、自己教師あり学習、強化学習などがあります。
(2) AIシステムに該当しないものの例
完全に手動で動作するよう設計されたシステムは自律性に欠けるとされます。また、自動的に操作を行うよう自然人によってのみ定義されたルールに基づくシステムは推論能力がないとされ、AIシステムに該当しません(前文12項)。ガイドラインは、AIシステムの射程外になるものとして、次の例を挙げています。
① 数理最適化を改善するシステムや、最適化手法を加速し、近似するために用いられるシステム(ガイドライン42項~45項)。機械学習に用いられるものであっても、これらはデータ処理の問題ととらえられています。具体例として、帯域幅の割当てやリソースの管理を最適化する衛星通信システムが挙げられています。
② 基本的データ処理に過ぎないもの(ガイドライン46項、47項)。推論はしないので、AIシステムの定義に該当しないとされます。具体例として、売り上げレポートを可視化するソフトウェアが挙げられています。
③ 古典的経験則に基づくシステム(ガイドライン48項)。具体例として、経験則評価関数によるmini-maxアルゴリズムを用いるチェスのプログラムが挙げられています。この例は、第一次人工知能ブームで取り上げられた手法です。
④ 単純な予測システムは、機械学習に基づくものであってもAIシステムの定義の射程外とされます。具体例として、気温予測のために先週の平均気温を用いるものが挙げられています(ガイドライン49項~51項)
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】【8/6開催】JRRC 著作権講座初級オンライン開催について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
先日延期のご案内を差し上げておりました「著作権講座初級オンライン」につきまして、
振替日程が下記の通り決定いたしましたので、ご案内申し上げます。
プログラムにつきましては、前回のご案内から変更はございません。
★開催日時:2025年8月6日(水) 13:30~16:35★
プログラム予定
13:30~15:05 第1部 著作権制度の概要
15:05~15:15 休憩
15:15~15:25 JRRCの管理事業について
15:25~16:35 第2部 死後の人格的利益の保護(八代亜紀さんの場合はどうなる)
★ 参加お申込みページ : https://jrrc.or.jp/event/250709-2/ ★
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━
【3】【7/31・8/20 開催】全国オンライン著作権セミナー開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ◇◆
このたび、全国の官公庁・民間企業の皆様を対象に、 著作権に関する実務セミナーを開催いたします。
情報発信の多様化やデジタル化が進む現代において、 著作権の適切な理解と対応は、業務運営上ますます重要性を増しています。
今回は、著作権のより一層の保護を図るために、 著作権の基礎知識の普及と複製を行う際に必要となる契約についてご案内させていただきます。
また、一般的な著作権(初級レベル) についての解説や著作物の正しい利用方法についてより詳しくご説明いたします。
〇開催要項
日 時 :【第1回】7月31日(木) 14:00~15:30
【第2回】8月20日(水) 14:00~15:30
会 場 :オンライン (Zoom/YouTube)
参加費 :無料
主 催 :公益社団法人日本複製権センター
参加協力:新聞著作権協議会(加盟68社) および日本経済新聞社、奈良新聞社
〇プログラム(予定)
【第1回】
トピックス1 著作権の集中管理と適正利用について
トピックス2 新聞の紙面ができるまで
トピックス3 新聞記事を巡る著作権侵害の事例 ~リスクを避けてクリッピング活用を~
トピックス4 著作物の複製等に関する利用許諾の取得について
【第2回】
トピックス1 著作権の集中管理と適正利用について
トピックス2 新聞の紙面ができるまで
トピックス3 新聞記事を巡る著作権侵害の事例
トピックス4 著作物の複製等に関する利用許諾の取得について
参加お申込みページ:https://jrrc.or.jp/event/250703-2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。 お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。
□読者登録、 配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、 HP よりお申込みください 。
(見積書の作成も可能です )
⇒https://jrrc.or.jp/
ご契約窓口担当者の変更
⇒https://duck.jrrc.or.jp/
バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
お問い合わせ窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益社団法人日本複製権センター (JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/
※このメルマガはプロポーショナルフォント等で表示すると改行の 位置が不揃いになりますのでご了承ください。
※このメルマガにお心当たりがない場合は、お手数ですが、 上記各種お手続きのご意見・ご要望よりご連絡ください。