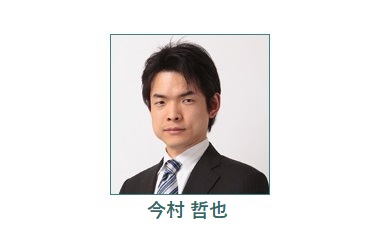━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン No.413 2025/4/3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】今村先生のイギリス著作権法の特徴を捉える(初級編)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
本日4月3日は「日本橋開通記念日」
1911(明治44)年のこの日、日本橋が木の橋から石造りに改築されて開通式が行われました。
現在も残っている石造りの日本橋は、国の重要文化財に指定されています。
さて、今回は今村哲也先生のイギリスの著作権制度についてです。
今村先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/imamura/
◆◇◆【1】イギリス著作権法の特徴を捉える(初級編)━━━
Chapter 33. イギリスにおける放送の著作権
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
明治大学 情報コミュニケーション学部 教授 今村哲也
1.はじめに
テレビやラジオなどの放送は、私たちの日常生活にとって重要な情報源であり娯楽です。放送は多くの人々の努力や投資によって生み出されるため、著作権法でもその権利を守っています。しかし、放送に関する放送事業者の権利に関しては国ごとに保護の方法や考え方が異なる場合があります。
特にイギリスは著作隣接権という制度がありませんので、放送を著作隣接権で保護している日本の法制度との違いは顕著です。今回はイギリスの著作権法に焦点を当て、日本との違いを交えながら、放送事業者がどのように法的に保護されているのかを見ていきましょう。
2.放送に関する権利の位置づけ
日本の著作権法では、放送事業者による放送は「著作隣接権」という、著作権とは別枠の権利で保護されています。一方で、イギリスの著作権法(Copyright, Designs and Patents Act 1988)では、放送それ自体を独立した著作物(work)として規定しており、著作権によって直接に保護しています(著作権法第1条1項(b)号)。これは日本の著作権法との最も大きな違いです。
このようにイギリス法では、放送そのものを著作物として保護しており、放送事業者は著作物の著作権者として番組の複製や配布、公衆への伝達(再放送、オンライン配信など)を管理できるのです。
もっとも、このことはイギリスの著作権法において放送事業者が放送される放送番組について著作権を持つ場合があることを否定しているわけではありません。放送事業者が創作性のある放送コンテンツ(演劇の著作物、映画、録音物など)を制作すれば、コンテンツについての著作権と、放送自体の著作権の両方を取得することになります。
この点については、日本の放送事業者が放送されるコンテンツを自ら制作したときに、放送に関する著作隣接権と、放送されるコンテンツ(映画の著作物など)についての著作権とをもつのと同様です。
3.放送の著作権の範囲と内容
放送の著作権に関するイギリス著作権法の具体的な保護内容は、著作権法第6条に規定されています。これによると、「放送」とは、視覚的影像、音声、その他情報を電子的に送信することで、公衆が同時に受信することを意図しているもの、あるいは特定の時間に公衆に提供されるものを指します(著作権法第6条1項参照)。
この定義は非常に広く、有線・無線の両方を含み、テレビやラジオ、衛星放送、デジタル放送などあらゆる形態の放送が対象となります。
放送についての権利の定め方については、日本とイギリスの著作権法では若干異なります。これは日本では放送が著作隣接権の対象物であるのに対して、イギリスでは著作物に分類されることに起因します。
日本の著作権法では、放送に関する放送事業者の著作隣接権は個別に規定されています(日本の著作権法98条から100条参照)。
これに対して、イギリスにおける放送の権利は、著作物の著作権として保護されるので、規定の仕方が異なります。
具体的にいうと、イギリス著作権法では著作物の著作権について、16条から21条において、規定されているのですが、それらの規定では、(1)「著作権のあるあらゆる種類の著作物の著作権により制限される行為」として放送を含むすべての著作物について与えられる権利と、(2)「次に掲げる著作物の著作権により制限される行為」という規定の仕方で一部の著作物に対して与えられる権利とに分ける方式をとっています。
たとえば、複製権について規定する17条は、「著作物の複製は、著作権のあるあらゆる種類の著作物の著作権により制限される行為である」とし、放送も含んでいます。
それに対して、公の実演に関する権利について規定する19条は、「著作物の公の実演は、文芸、演劇又は音楽の著作物の著作権により制限される行為である。」とされ、放送は含まれていません。
条文をみると、放送の著作権として与えられている権利は、複製(17条)、複製物の公衆への配布(18条)、公衆への伝達(20条)に対するものに限られています。なお、公衆への伝達は、放送とオンデマンド方式での公衆への提供を含むとされています(20条2項(a)(b))。
放送の著作権については、日本法と同様(日本著作権法101条1項3号・2項3号)、放送後50年の保護期間が与えられています(イギリス著作権法14条2項)。この期間中は無断での録音・録画(固定)とその配布、(放送の再)放送・オンデマンド配信などが禁止されることになります(16条および20条)。
なお、再放送(リピート放送)による延長はありません(14条5項)。この点は、日本の著作権法と同様です(日本著作権法102条)。
4.放送に関する著作権の意義と判例の動向
イギリスで放送の著作権が認められる背景には、放送事業者が行う多大な投資を法的に保護する狙いがあります。放送番組の制作には巨額の費用がかかりますが、こうした費用を回収するためには、放送だけでなく、その二次利用(オンライン配信やDVD販売)することが重要なのです。
特にイギリスの放送局はその事業を世界的に展開しており、全世界における放送とそのコンテンツ保護にきわめて熱心だといえます。
また、特にサッカーのプレミアリーグといったスポーツ中継などの放送については、インターネットで同時配信されて侵害される事例があり、深刻に受け止められています。
こうしたなか、ネット時代においては、放送に関する公衆への伝達(20条)の権利も、裁判所によって権利範囲はより幅広く解されています。
具体的にいうと、ITV Broadcasting Ltd and others v TVCatch Up Ltd事件( [2010] EWHC 3063 (Ch), 25 November 2010)では、インターネット上で地上波テレビ番組を同時配信していたTVCatchup社に対し、放送局側(ITV等)が著作権法20条(公衆への伝達権)侵害を主張がなされました。
TVCatch Up社側は、同社による配信は「1対1」の配信であるため、「公衆への伝達」に含まれないと主張しましたが、高等裁判所のキッチン裁判長は、著作物の公衆への伝達の定義は、電子的送信によって著作物を公衆に伝達するすべての行為を対象とし、放送(20条1項(a))とオンデマンド配信(同項(b)号)という2つの伝達手段に限定されるものではないとしました。
この裁判は、イギリスが当時は加盟していたEUの情報社会指令の規定をめぐる法解釈について明確にする必要があったために、欧州司法裁判所にも付託されましたが、同様の判断がなされました(ITV Broadcasting Ltd v TVCatchup Ltd, CJEU Case C-607/11 (2013))。
結論として、イギリス著作権法では、放送を許可なくインターネットで同時配信する行為は、著作権法20条の公衆への伝達権を侵害するということになり、放送事業者の権利がより強固なものであることが確認されたことになります。
なお、日本では、放送を受信して行われる無許可のネット同時配信は、放送事業者の送信可能化権(日本著作権法99条の2)で対応が可能であると思われます。
他方でTverやNHKプラスなどで行われている正規の「放送のネット同時配信」を第三者がさらに無断で再配信する行為は、解釈論上、放送の著作隣接権では対応が難しいと解されるので、放送番組の著作権に関する公衆送信権(日本著作権法23条1項)によって対応することになるでしょう。
なぜ解釈論として難しいかというと、日本の著作権法の条文では、「放送を受信して・・・その放送を送信可能化する」ことが、放送の送信可能化権の対象になっており(日本著作権法99条の2)、放送と同内容のものがネットで同時配信されているとしても、それは放送の同時配信であり、放送そのものではないからです。
とはいえ、無断の再配信の元が放送経由なのか、放送局が行なっている同時配信経由なのかによって、法的結論が区別されるのは、放送同時配信が放送局の通常のサービスとして行われている時代に、やや違和感があるかもしれません。
5.放送事業者保護の国際的な課題
近年のインターネットの普及に伴い、無許可のオンライン再送信や海賊放送が増えています。放送を無許可で同時配信して、その際に無断で広告をつけたりするのです。
また、日本でもTverやNHKプラスなどで行われていますが、いわゆる放送の見逃し配信なども、世界中の放送局がサービスとして行なっている実態があります。
スマホやPCの画面で動画をみる時代において、放送のオンライン上での無断配信は、今後とも世界的な問題となっていくでしょう。
これまでは言語の壁もありましたが、今の時代、AIを使えば簡単に字幕もできますので、海外の面白い放送やその同時配信をネットにおいて無断で再配信して、勝手に自国語の字幕や広告をつけるといったことはますます容易にできるはずです。
こうした海賊行為に対抗するため、イギリスを含む各国が連携して放送機関を保護する新しい国際条約作成の取り組みを世界知的所有権機関(WIPO)のSCCR(著作権等常設委員会)で進められています。特に強い保護を推し進めているのは、EUです。
この放送機関に関する新条約の交渉は、実はすでに四半世紀を超えて行われているのですが、各国間での意見調整が難航しており、まだ条約は成立するに至っていません。
6.おわりに
イギリスの著作権法は、放送事業者がその投資を回収し、多様なコンテンツを生み出せるように著作権制度によって法整備をしています。
権利の建て付けとしては、イギリス著作権法は、日本の著作隣接権制度とは異なる方法を採っていますが、放送事業者の権利を保護するという点ではそれほど違うわけではありません。
実は、著作隣接権制度のうち、放送事業者の権利については、著作権法の教科書でもあまり詳しくは述べられていないことが多く、述べられていたとしても、放送関係者でないかぎり実感として理解するのは難しいものです。
ですが、イギリスの法制度と比較することで、日本の著作権法が放送をどのように保護しているのかという理解も、少しは深まるかもしれません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。
□読者登録、配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、HPよりお申込みください。
(見積書の作成も可能です)
⇒https://jrrc.or.jp/
ご契約窓口担当者の変更
⇒https://duck.jrrc.or.jp/
バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
お問い合わせ窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/
編集責任者
JRRC代表理事 川瀬 真