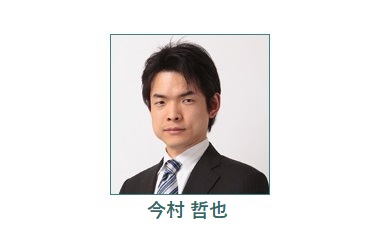━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン No.417 2025/5/8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】今村先生のイギリス著作権法の特徴を捉える(初級編)
【2】2025年度著作権講座初級オンライン開催について(無料)受付中!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
本日5月8日は「松の日」
日本の松を守る会が1989年に制定。
1981年のこの日、初めて同会の全国大会が開催され、
日本の代表的な樹木の松をいつまでも大切に保護して行くことを目的とされています。
さて、今回は今村哲也先生のイギリスの著作権制度についてです。
今村先生の記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/imamura/
◆◇◆【1】イギリス著作権法の特徴を捉える(初級編)━━━
Chapter 34. イギリスにおける音楽産業と著作権(1)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
明治大学 情報コミュニケーション学部 教授 今村哲也
1. はじめに
イギリスの音楽産業は、イギリスの国内経済に大きな貢献をしています。UK Musicの2024年レポート「This is Music 2024」
同年の音楽産業の輸出収入も46億ポンド(約8,720億円)と過去最高を記録し(前年比15%増)、雇用者数も約21万6千人に増加しています。これらの数字は、パンデミックからの回復とともに音楽産業が再び成長軌道に乗っていることを示しています。
今回は、イギリスの音楽産業の現状とその市場構造について、著作権関連の関連団体の仕組みにも触れながら概観します。
2. 市場トレンド:ストリーミングの台頭とアナログ復興
デジタル化・ネットワーク化のトレンドにより、イギリスの音楽市場はストリーミング主導に変化しています。BPI(英国レコード産業協会)のデータによると、2023年には音楽の消費量の約88%がストリーミングによるもので、年間ストリーミング再生数は1,796億回に達し前年から12.8%増加しました(BPIウェブサイト, Women enjoy a record-breaking year in music in 2023,
ストリーミング市場の拡大に伴い、英国内で消費される音楽の総量(アルバム換算)は前年比10%増の1億8,280万のアルバム分に相当する規模となっていると言われています(前掲・BPIウェブサイト)。
一方で、物理メディア市場も依然として存在感をもっています。特にアナログレコードは復活傾向が顕著で、販売数は16年連続で増加し、2023年には610万枚と前年比11.8%増を記録しました(前掲・BPIウェブサイト)。
イギリスの音楽市場ではデジタルの占める割合が圧倒的となりつつも、アナログ盤のような物理メディアもコアなファン層に支えられて市場の一部を占めるという二極化ともいえるトレンドが見られます。
3. 音楽産業を支える主なプレーヤー
イギリスの音楽産業は、多様なプレーヤーによって構成されています。
アーティスト(ミュージシャン)は、音楽産業の中心的な存在となります。アーティストは楽曲を創作・演奏し、その創造力が産業の原動力となります。しかし、他のエンターテイメント産業と同様、いくら個々のアーティストに才能があっても、それだけで音楽が巨大な産業になることはありません。
音楽を産業として成功させる上でもっとも重要な役割を果たすのは、レコードレーベル(レコード会社)です。レーベルは、アーティストと契約し、楽曲の録音制作、プロモーション、流通販売などを担う企業で、大手レーベルは世界規模のネットワークを通じてアーティストの楽曲を市場に届けるという役割を果たします。
アーティストやレーベルがどんなにすばらしい楽曲や歌詞やレコードを作っても、それを利活用しなければさらなる利益は生じません。
音楽出版社(ミュージック・パブリッシャー)は作詞家・作曲家から楽曲の著作権を預かりその著作権管理を行い、楽曲の印税管理や他メディアへの利用許諾(例:映画やCMでの楽曲使用許可)などを進める役割を担います。これにより、著作権を含めた権利の価値を最適化することができ、作曲者らは著作権の使用料収入を得ることができます。
さらに重要なのが権利管理団体です。権利管理団体は著作権者に代わって音楽の利用許諾と使用料徴収を行う団体で、後述するようにイギリスでは作家向けのPRS for Music(PRSおよびMCPSの2団体からなる組織)や、レコード製作者・実演家向けのPPLなどが存在します。
加えて、この産業にはマネージャーやプロモーター、ライブ会場運営者など多数の関連職種が関わっていますが、アーティスト・レーベル・音楽出版社・権利管理団体の四者が特に主要なプレーヤーと言えます。
イギリスではこれらの関係者が業界団体であるUK Musicの下で連携しています。UK Musicのメンバーは、Association of Independent Music(AIM)、British Phonographic Industry(BPI)、Featured Artists Coalition(FAC)、Ivors Academy(旧BASCA)、Music Managers Forum(MMF)、Music Producers Guild(MPG)、Music Publishers Association(MPA)、Musicians’ Union(MU)、そしてPPLおよびPRS for Musicから構成されています。(G. Harbottle, N. Caddick, U. Suthersanen (Harbottle et al.), Copinger and Skone James on Copyright (19th edition, Sweet & Maxwell 2025) para, 29-128)。
このように多面的なプレーヤーが協働することで、音楽の創作から流通・利用許諾までのエコシステムが機能しているのです。
4. メジャーとインディペンデント:構造と役割の違い
レコードレーベルには大きく分けてメジャー(大手)とインディペンデント(独立系)があります。現在、世界の音楽レーベル市場はユニバーサル・ミュージック、ソニー・ミュージック、ワーナー・ミュージックという3社のメジャーが支配しており、2022年時点でいえば、この「ビッグ3」が世界レコード市場の約70%を占めました (Harbottle et al., para, 29-127)。
メジャーレーベルは豊富な資金力と国際的ネットワークを活かし、大規模なマーケティングや新人開発、グローバル展開に強みを持っています。
一方、インディペンデント・レーベルは比較的小規模ながら独自の個性あるアーティストやニッチなジャンルを育成する役割を担い、音楽シーンの多様性を支えています。イギリスではインディー音楽のシーンも非常に活発で、BPIの年次報告によれば独立系レーベルからのリリースが2023年の国内音楽消費の約29.2%を占め、2017年以降着実にシェアを伸ばしています (前掲・BPIウェブサイト)。
5. イギリスにおける権利管理団体(PRS, PPL, MCPS)の機能と連携
イギリスでは、音楽著作権に関する権利管理は主にPRS for MusicとPPLの二本柱で運用されています。PRS for Music(Performing Right Society for Music)は作曲家・作詞家(著作権者)向けの著作権管理団体で、楽曲の演奏権や公衆送信権といった楽曲(作詞・作曲)に対する権利を管理します。
PRS for Musicは実体としてはPRSとMCPS(Mechanical-Copyright Protection Society)の2団体から成り、PRSが演奏やストリーミングなど公で音楽を利用する際の使用料を徴収・分配し、MCPSはCDやダウンロード等で楽曲を複製・頒布する際の使用料(機械的複製権料)を管理します(Harbottle et al., paras, 29-132, 133)。
PRSとMCPSはいずれも作家・音楽出版社をメンバーとし、現在では「PRS for Music」の名の下で一体的に運営されています。PRSは使用料を年4回分配し、MCPSは月次で分配を行うなど運用面で異なるものの、作詞作曲者にとっては自身の楽曲が演奏・配信・販売される際に発生するロイヤルティを包括的に管理してくれる存在です。
これに対しPPL(Phonographic Performance Limited)はレコード製作者としてのレーベルやアーティストとしての実演家のための権利管理団体で、録音物(マスター音源)に関する権利を管理しています。具体的には、音源がラジオやテレビ、商業空間で流される際の使用許諾を与え、その使用料をレコード会社と実演家に分配します(Harbottle et al., para, 29-146)。
PPLには演奏者やレーベルが加入し、自分の関与する録音物が公で利用された際の報酬を受け取ることができます。例えば、ラジオ局が楽曲を放送で流す場合、曲の作曲者に対してはPRS for Musicが、録音物の権利者に対してはPPLがそれぞれ使用料を徴収し分配します。
なお、イギリスでは2018年にPRSとPPLが共同出資でPPL PRS Ltdという会社を設立し、店舗や商業施設向けに音楽利用の包括ライセンス(TheMusicLicence)を一本化して提供する体制も整えています (PPL PRSのウェブサイト
これにより事業者は窓口一つで楽曲の演奏権と録音物の使用権の両方をクリアでき、権利者側も漏れなく使用料を回収できる仕組みになっています。
以上のように、イギリスでは権利の種別(楽曲か録音物か)に応じて複数の専門団体が機能し、相互に連携しつつ、権利者に対して公平な報酬を配分することを実現しています。
6. おわりに
今回は、イギリスの音楽産業の現状とその市場構造について概観しました。日本は米国に次ぐ世界第2位の音楽市場規模を有し、イギリス(世界3位~4位規模)より市場規模では大きいのが現状です。もっとも、その収益構造は異なっている部分もあるようです。次回は、日本の音楽産業との比較を著作権・著作隣接権を切り口に見ていく予定です。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】2025年度著作権講座初級オンライン開催について(無料)受付中!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
今年度最初の著作権講座(初級)を5月28日(水)にオンラインで開催いたします。
本講座は著作権法を学んだことのない初心者向けの講座です。著作権法の体系に沿って著作権制度の概要を分かり易く解説するとともに、理解を深めるために重要判例や最新の情報についてもお話いたします。
参加ご希望の方は、著作権講座受付サイトよりお申込みください。
★開催日時:2025年5月28日(水) 13:30~16:35★
プログラム予定
13:30~15:05 第1部 著作権制度の概要
15:05~15:15 休憩
15:15~15:25 JRRCの管理事業について
15:25~16:35 第2部 最近の著作権制度の課題等
★ 受付サイト:https://jrrc.or.jp/event/250501-2/ ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。
□読者登録、配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、HPよりお申込みください。
(見積書の作成も可能です)
⇒https://jrrc.or.jp/
ご契約窓口担当者の変更
⇒https://duck.jrrc.or.jp/
バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
お問い合わせ窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/
編集責任者
JRRC代表理事 川瀬 真