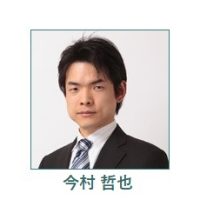━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジン No.414 2025/4/10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※マガジンは読者登録の方と契約者、関係者の方にお送りしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆今回の内容
【1】板東氏のコンプライアンス・企業倫理を考える
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
本日4月10日は「四万十の日」
四万十の美しい流れと豊かな自然を守り、後世に伝えていくため、高知県四万十市が2009年に制定されたそうです。
さて、今回は板東氏の「コンプライアンス・企業倫理を考える」の連載の最終回です。
板東氏の前回までの記事は下記からご覧いただけます。
https://jrrc.or.jp/category/bando/
◆◇◆【1】板東氏のコンプライアンス・企業倫理を考える━━━
⑪ 立法の動向・終わりに
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
日本赤十字社常任理事/雪印メグミルク株式会社社外取締役 板東久美子
この連載では、コンプライアンス・企業倫理に関する様々なテーマを取り上げてきましたが、今回で最終回となりました。今まで公益通報者保護法の改正の検討や、AIに関する法制の検討についても触れましたが、最近、これらの検討がまとまり、法案が通常国会に提出されています。今回は、このようなコンプライアンスを考える上で重要な法制の最近の動きについてご紹介したいと思います。
しかし、コンプライアンス・企業倫理の実践には、細かい法令・ルールを知ることが重要なのではありません。いわば適切な行動・判断のためのマインドセットや「体幹」を鍛えることが重要であることを述べて、しめくくりたいと思います。
公益通報者保護法改正法案
公益通報者保護法の改正については、この連載においても第7回(2024年12月)に消費者庁の公益通報者保護制度検討会における検討について、特に公益通報を理由とする不利益取扱についての罰則導入に関する議論をご紹介しました。その検討結果に基づく公益通報者保護法一部改正法案が本年3月4日に閣議決定されました。その内容は、以下の4つの柱からなっています。
①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上
現行法では、内部通報体制の整備のため、事業者(300人超の常時勤務者を雇用する場合)は、公益通報を受けて対象事実の調査やその是正に必要な措置をとる業務に従事する「公益通報対応業務従事者」を指定することが義務付けられていますが、その指定義務に違反する場合には、権限ある行政機関が指導・助言、勧告ができることになっています。今回の改正法案では、その勧告に従わない場合の行政機関の命令権と、命令違反の場合の30万円以下の罰金刑(両罰)を新設しています。また、そのような事業者に対する現行の報告徴収権に加えて立ち入り検査権を設け、報告懈怠や虚偽報告、検査拒否に対する30万円以下の罰金刑を新設しています。
②公益通報者の範囲拡大
保護される「公益通報者」の範囲に、事業者と業務委託関係のある、又はそれが終了して1年以内のフリーランスを追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取り扱いを禁止することとしています。
③公益通報を阻害する要因への対処
事業者が、労働者等に対し、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為を禁止し、そのような合意を無効としています。また、事業者が、正当な理由なく、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止しています。
④公益通報を理由とする不利益な取り扱いの抑止・救済の強化
公益通報を理由とする不利益取扱いについては、現行法では、公益通報を理由とする解雇の無効とそれ以外の不利益取り扱いについての禁止が規定されていますが、その違反については民事救済に委ねられており、その実効性が問題となってきました。改正法案では、通報後1年以内の解雇や懲戒は、公益通報を理由としてされたものと推定し、民事訴訟上の立証責任を転換しています。また、公益通報を理由として解雇や懲戒を行ったものに対する罰則(6月以下の拘禁、又は30万円以下の罰金)も新たに導入しています。
兵庫県知事をめぐる事例でも、公益通報者を探索する行為や通報者に対する懲戒処分などが問題となりました。この法案の成立により、公益通報者保護制度の実効性が高まることが期待されます。
AI法案
発達めざましいAIについては、倫理上のリスク・課題もいろいろ指摘されており、EUの規制法や米国の動き、広島プロセスや日本での法整備の検討などについて連載第8回(2025年1月)でご紹介しました。EUにおいては、一定の規制を導入する法の施行を迎える一方、米国では、トランプ大統領就任後、バイデン政権下の大統領令を廃止し、AIの規制を行わない方向に舵を切っています。我が国は、このたび、AIについての基本法である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(AI法案)」がまとまり、2月28日に国会に提出されました。
この法案では、法律の目的として、AIが我が国の経済社会の発展の基盤技術であることに鑑み、AIの研究開発・活用の推進施策について、基本理念や基本計画策定等の基本事項を定めるとともに、総理大臣をトップとして全閣僚で構成する「人工知能戦略本部」を設置し、その総合的・計画的推進を図り、国民生活の向上、国民経済の健全な発展に寄与することとしています。
そして、基本理念としては、1)AIが効率化・高度化、新産業創出といった経済社会の発展の基盤技術であるとともに、安全保障の観点からも重要な技術であることに鑑み、我が国のAIの研究開発力を保持し、国際競争力を向上、 2)基礎研究から活用まで総合的・計画的に AI 推進、 3)適正な研究開発・活用のため透明性を確保、4) 国際協力において主導的役割を発揮することを定めています。さらに、 基本施策としては、① 研究開発の推進、施設等の整備・共用の促進 ② 人材確保、 教育振興、③ 国際的な規範策定への参画、 適正性のための国際規範に即した指針の整備、 ④ 情報収集、権利利益を侵害する事案の分析・対策検討 ⑤ 事業者・国民への指導・助言・情報提供 などを規定しています。
ここには、AIに関し、世界のモデルとなる 制度を構築し、 国際指針に則り、イノベーション促進とリスク対応を両立したいという考えが法整備の根底にあります。EUのようなハイリスクAIに関する強い規制などを行う型でも、政府がコミットしない米国型でもない行き方を指向しているといえます。権利侵害などに対しても、新たな法的規制は規定されておらず、国は、不正な目的・不適切な方法によるAIの研究開発・活用に伴って権利利益が問題となる事例を分析及びそれに基づく対策を検討し、その結果に基づいて研究開発者・事業者等に指導・助言・情報提供することにとどめています。AIに関する基本法としての第一歩を踏み出したものであり、今後の技術進展や社会変化、国際的動向を踏まえた施策面での進展が期待されるところです。
終わりに
1年近くにわたり、公益通報者保護法と内部通報制度、AI関連法制、個人情報保護法など、関係深いいろいろな法制度のご紹介も含めて、コンプライアンス・企業倫理の推進の在り方について綴らせていただきました。しかし、法令や基準・ルールを知ること以上に重要なのは、確かな判断・行動の軸を確立するとともに、多角的な視点により検証することであると思います。判断軸として重要なのは、まさに「持続可能性」「説明可能性」「公正・誠実」という視点であると思います。
例えば、著作物の利用について考える時、著作権法の規定のどこに当たるか、厳密に違法かどうかを考える以前に、著作者の利益を軽視することになり、著作物の創作の淵源に経済的・精神的に影響を与えることにならないか、持続可能な創作のサイクルを脅かすことにならないか、社会的に説明できるかを考えるマインドを確立することが重要であると思います。
私自身、公金不正支出問題直後の秋田県に出向した時、常に組織外からの視点、県民の視点を意識することの重要性を痛感し、判断・行動の軸が変わってきました。今までご紹介した雪印メグミルクの例も、問題が起きたことを「風化させない」、望ましくない状態を当たり前のものとして「風景化しない」ことを強く学ぶ契機となりました。
様々な問題についてこのような積み重ねで体幹を鍛えることにより、まさに「思うままに従い、矩(のり)を踰えず」に近づいていくことが、私自身の願いでもあります。
最後までまとまりのない連載となりましたが、皆様それぞれの組織・活動の中で、このコンプライアンス・企業倫理の体幹を意識して鍛えていただくきっかけに少しでもなれば幸いです。著作権制度の適正な運用に関わっておられる皆様のご努力が、当たり前の行動軸として社会で確立していくことを心より期待し、連載の終わりとさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JRRCマガジンはどなたでも読者登録できます。お知り合いの方などに是非ご紹介下さい。
□読者登録、配信停止等の各種お手続きはご自身で対応いただけます。
ご感想などは下記よりご連絡ください。
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
■各種お手続きについて
JRRCとの利用契約をご希望の方は、HPよりお申込みください。
(見積書の作成も可能です)
⇒https://jrrc.or.jp/
ご契約窓口担当者の変更
⇒https://duck.jrrc.or.jp/
バックナンバー
⇒https://jrrc.or.jp/mailmagazine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
お問い合わせ窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
⇒https://jrrc.or.jp/contact/
編集責任者
JRRC代表理事 川瀬 真
※このメルマガはプロポーショナルフォント等で表示すると改行の位置が不揃いになりますのでご了承ください。
※このメルマガにお心当たりがない場合は、お手数ですが、上記各種お手続きのご意見・ご要望よりご連絡ください。